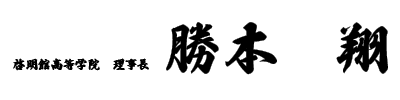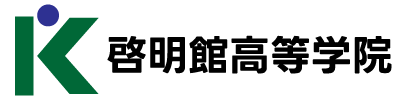理事長あいさつ
理事長挨拶 ~真の教育革新への挑戦~
はじめに
この度、兵庫県丹波市という豊かな自然と歴史ある文化に包まれた地に、啓明館高等学院を開校するという歴史的な節目を迎えるにあたり、地域の皆様、教育関係者の皆様、そして全ての方々に心からのご挨拶を申し上げます。
私たちが今回立ち上げる啓明館高等学院は、単なる教育機関の新設という枠組みを大きく超えた、社会変革への壮大な挑戦です。現代社会が直面する複雑で多層的な課題群に対し、教育という最も根源的で強力な手段を通じて、統合的かつ持続可能な解決策を提示することを使命としています。私たちのビジョンは、すべての人が自己の内に秘められた無限の可能性を最大限に開花させ、それを他者と社会全体の豊かさへと還元する「循環する社会の仕組み」を創造することにあります。
現代社会への問題意識と私たちの立場
21世紀に入り、私たちの社会は前例のない速度で変化し続けています。グローバル化、デジタル化、少子高齢化、環境問題、格差拡大、価値観の多様化など、様々な潮流が複雑に絡み合い、従来の教育システムでは対応しきれない状況が生まれています。特に深刻なのは、画一的な教育制度の中で、多様な個性や才能を持つ子どもたちが適切な学習環境を見つけられずにいることです。
不登校の児童生徒数は年々増加の一途を辿り、その背景には学校での人間関係の困難、学習内容への適応困難、家庭環境の複雑化など、多岐にわたる要因が存在します。いじめという深刻な人権侵害は依然として根絶されず、被害を受けた子どもたちの心に深い傷を残し続けています。さらに、家庭内での虐待や暴力は、子どもたちの人格形成に計り知れない影響を与え、学習への意欲や人間関係への信頼を根底から揺るがしています。
また、医学的な配慮を必要とする子どもたちも少なくありません。喘息による体調の変動、透析治療による通学時間の制約、てんかんへの理解不足による社会的偏見、糖尿病管理の複雑さ、精神疾患に対する周囲の無理解など、様々な医学的事情が教育機会の平等を阻害している現実があります。
これらの課題に対し、既存の教育制度は十分に応えきれていません。むしろ、標準化された枠組みの中で、「普通」から外れる子どもたちを排除し、彼らの可能性を見過ごしてしまっているのが現状です。私たちは、このような状況を根本的に変革する必要があると強く確信しています。
「異才」という概念への深い理解
啓明館高等学院が最も大切にする概念の一つが「異才」です。この言葉は、従来の教育制度や社会の価値観では十分に評価されてこなかった、多様で独特な才能や能力を指しています。異才とは、決して「変わった人」や「問題のある人」を意味するのではありません。むしろ、既存の枠組みにとらわれない独創的な思考力、深い感受性、他者への共感力、創造的な表現力、独特な視点から物事を捉える力など、社会の発展にとって不可欠な資質を持つ人々のことです。
歴史を振り返ってみても、人類の進歩に大きく貢献した偉大な人物たちの多くは、同時代の「普通」の基準からは外れた存在でした。アインシュタインは幼少期に言語発達の遅れがあり、エジソンは学校教育に適応できず家庭で学びました。スティーブ・ジョブズは大学を中退し、既存の概念を覆すような革新的な製品を生み出しました。彼らが偉大な業績を残せたのは、その「異才」が適切に理解され、伸ばされる環境があったからです。
私たちは、現代社会にも数多くの「異才」が存在していると確信しています。しかし、画一的な教育制度や社会の偏見により、その才能が埋もれてしまっているケースがあまりにも多いのです。啓明館高等学院は、そのような隠れた才能を発見し、適切に育成し、社会全体の利益につなげていく役割を担います。
包括的な学習環境の構築
啓明館高等学院では、どのような背景や状況にある生徒でも、安心して学習に取り組める環境を整備します。これは単なる物理的な配慮にとどまらず、心理的、社会的、医学的な支援を統合した包括的なアプローチです。
心理的サポート体制
不登校や学校でのトラブルを経験した生徒に対しては、まず心の回復を最優先に考えます。専門的なカウンセリング体制を整備し、一人ひとりの心理状態や学習への準備度に応じて、個別的な支援計画を策定します。無理に従来の学校生活に適応させるのではなく、その生徒にとって最も適切な学習スタイルや人間関係のあり方を一緒に探求していきます。
いじめや虐待の経験により人間関係に困難を感じる生徒には、安全で信頼できる人間関係を段階的に構築できるよう、少人数制のクラス編成や、個別指導の時間を十分に確保します。他者との関わりを強制するのではなく、その生徒のペースに合わせて、徐々に社会性を回復していけるよう、継続的な支援を行います。
医学的配慮の徹底
医学的な事情を抱える生徒に対しては、医療従事者と連携した専門的な支援体制を構築します。喘息の生徒には清潔で適切な湿度管理された学習環境を提供し、必要に応じて学習時間の調整や休息時間の確保を行います。透析治療を受けている生徒には、治療スケジュールに合わせた柔軟な時間割編成や、遠隔学習システムの活用により、継続的な学習機会を保障します。
てんかんを持つ生徒に対しては、教職員全体が適切な対応方法を理解し、発作時の安全確保と心理的支援を行います。同時に、他の生徒たちにも正しい理解を促し、偏見や差別のない学習環境を作り上げます。糖尿病の生徒には、血糖値管理や食事療法への配慮を行い、医学的管理と学習活動のバランスを取れるよう支援します。
精神疾患を抱える生徒に対しては、専門医やカウンセラーと密接に連携し、投薬管理や症状の変化への対応を適切に行います。周囲の理解を深めるための教育も重視し、すべての生徒が多様性を受け入れる人間性を育めるよう取り組みます。
革新的な教育カリキュラムの展開
啓明館高等学院の教育は、従来の詰め込み型学習から大きく転換し、生徒一人ひとりの興味関心や将来の目標に応じたオーダーメイドの学習プログラムを提供します。
自己理解の深化
教育の出発点は、生徒自身が自分を深く知ることです。自分の強みや弱み、興味関心の方向性、価値観や人生観、学習スタイルの特徴などを多角的に探求します。これには様々な心理学的手法や、体験学習、創作活動、対話セッションなどを活用します。自己理解が深まることで、生徒は自分らしい学習方法や将来の方向性を見つけることができます。
多様性理解教育
現代社会で最も重要な能力の一つが、多様な価値観や背景を持つ他者を理解し、協働できる力です。啓明館高等学院では、様々な文化的背景、宗教的信念、生活環境、身体的特徴、思考様式を持つ人々について学び、直接的な交流の機会も多く設けます。これにより、偏見や差別を乗り越え、真の意味でのインクルーシブな社会の実現に貢献できる人材を育成します。
社会課題解決型学習
学習内容を単なる知識として覚えるのではなく、現実の社会課題の解決に活用する実践的な学習を重視します。環境問題、貧困、高齢化、地域活性化、国際協力など、様々な課題に対して、生徒たちがチームを組んで調査研究し、具体的な解決策を提案し、実際に行動に移す機会を提供します。この過程で、学問的知識と実践的スキルの両方を身につけることができます。
創造性と表現力の育成
すべての生徒が持つ創造的な才能を発見し、伸ばすための多様な表現活動を展開します。芸術、音楽、文学、演劇、映像制作、デザイン、プログラミング、起業体験など、幅広い分野で自己表現の機会を提供します。表現活動を通じて、生徒は自分の内面を外に向けて発信する力を養い、他者とのコミュニケーション能力も向上させます。
多角的な成功観の提示
現代社会では、往々にして経済的成功や社会的地位の高さのみが「成功」として評価される傾向があります。しかし、啓明館高等学院では、より多角的で人間的な成功観を提示し、生徒たちがそれぞれの価値観に基づいた人生設計ができるよう支援します。
真の成功の定義
私たちが考える真の成功とは、「自分を含めて守るべきものを守ることができる」状態です。これには、自分自身の心身の健康、家族や友人との良好な関係、地域社会への貢献、自然環境の保護、次世代への責任など、多層的な要素が含まれます。年収の高低や職業の社会的威信だけで人生の価値を測るのではなく、どれだけ多くの人や物事を幸せにし、守ることができたかを重視します。
多様な生き方の肯定
日本の経済と社会を支えているのは、決して一部の大企業や有名人だけではありません。地域に根ざした中小企業、創意工夫を重ねる職人、地域課題に取り組むNPO職員、子育てに専念する親、介護に従事する人々、芸術文化を支える表現者など、様々な立場の人々がそれぞれの役割を果たし、社会全体を豊かにしています。
啓明館高等学院では、このような多様な生き方のすべてに価値があることを伝え、生徒一人ひとりが自分らしい人生の道筋を見つけられるよう支援します。起業家を目指す生徒には事業計画の作成や実践的なビジネススキルを、芸術家を目指す生徒には表現技術と作品発表の機会を、公務員を希望する生徒には社会制度の理解と市民サービスの意義を、それぞれに適した教育プログラムを提供します。
生涯学習と継続的成長の理念
啓明館高等学院の教育理念の根底にあるのは、「人生は死を迎えるその瞬間まで、学びと成長の旅である」という信念です。高校卒業や大学進学、就職といった節目は、決してゴールではなく、新たなスタートラインに過ぎません。
学び続ける姿勢の育成
変化の激しい現代社会においては、一度身につけた知識やスキルが永続的に通用するとは限りません。むしろ、常に新しい情報を取り入れ、既存の知識を更新し、新たな挑戦に取り組む姿勢こそが重要です。啓明館高等学院では、知識の暗記よりも、学習方法の習得、情報収集と分析の能力、批判的思考力、創造的問題解決力の育成に重点を置きます。
人生の最終的な目標
私たちが考える人生の最も尊いゴールは、その人生の終わりに周囲の人々から「ありがとう」と心から感謝され、惜しみなく送り出されることです。これは、その人が生涯を通じて他者や社会に与え続けた価値が認められ、愛され続けていることの証拠です。
このような人生を実現するためには、常に他者のことを思いやり、社会全体の幸福を考え、自分の能力や資源を惜しみなく分かち合う生き方が必要です。啓明館高等学院では、利己的な成功追求ではなく、利他的な貢献を通じた真の充実感を体験できるよう、様々な社会奉仕活動や地域貢献プロジェクトに参加する機会を提供します。
地域との共創と社会変革の拠点として
啓明館高等学院は、丹波市という地域に根ざしながらも、その影響力を全国、さらには世界に向けて発信していく拠点となることを目指しています。
地域課題への積極的関与
丹波市をはじめとする地方都市が直面している少子高齢化、人口減少、産業の空洞化、伝統文化の継承といった課題に対して、生徒たちが主体的に取り組みます。高齢者の生活支援、地域産業の活性化アイデア、観光資源の発掘と活用、伝統工芸の現代的アレンジなど、若い感性と創造力を活かした解決策を提案し、実行に移します。
新しい社会モデルの実験場
啓明館高等学院は、従来の教育制度や社会システムの限界を超えた、新しい社会のあり方を実験する場でもあります。多様性を前提とした組織運営、持続可能な経済活動、世代を超えた学び合い、国際的な連携と交流など、21世紀の社会が求める新しい価値観と行動様式を実践し、その成果を広く社会に発信していきます。
教育改革のモデルケース
私たちの取り組みが成功すれば、それは日本全国、さらには世界の教育改革のモデルケースとなる可能性があります。画一的な教育制度に限界を感じている多くの教育関係者や保護者にとって、新しい教育の可能性を示す具体例となることを願っています。
具体的な支援体制と施設設備
専門スタッフの配置
啓明館高等学院では、従来の教員だけでなく、様々な専門分野の人材を配置します。臨床心理士、スクールカウンセラー、作業療法士、看護師、栄養士、キャリアコンサルタント、起業家、芸術家、地域おこし協力隊出身者など、多様な背景を持つスタッフが連携して生徒をサポートします。
柔軟な学習環境
教室という固定的な空間にこだわらず、自然環境での野外学習、地域の企業や施設での実地研修、オンラインでの国際交流、創作活動のためのアトリエ空間、静寂な個人学習スペースなど、学習内容や生徒の特性に応じた多様な環境を提供します。
最新技術の活用
ICT機器を積極的に活用し、個別最適化された学習システム、バーチャルリアリティを使った体験学習、プログラミング教育、動画制作やデジタルアートの創作など、21世紀のスキルを身につけられる環境を整備します。
卒業後の継続的サポート
啓明館高等学院の使命は、生徒が卒業した後も続きます。
進路支援の充実
大学進学を希望する生徒には、その生徒の特性や興味に最も適した進学先を一緒に探し、受験対策から入学後の適応支援まで継続的にサポートします。就職を希望する生徒には、職業体験、インターンシップ、就職活動の支援、入社後のフォローアップまで包括的に支援します。
卒業生ネットワークの構築
卒業生同士の継続的な交流を促進し、互いに支え合いながら成長していけるネットワークを構築します。定期的な同窓会や交流イベント、先輩から後輩へのメンタリング制度、共同プロジェクトの実施など、生涯にわたる学び合いのコミュニティを形成します。
おわりに ~皆様への心からのお願い~
啓明館高等学院の開校は、私たち一人の力では決して実現できません。地域の皆様、教育関係者、医療従事者、企業経営者、行政関係者、そして何より保護者の皆様のご理解とご協力があってこそ、この壮大な教育実験を成功させることができます。
私たちは、この学院を通じて、「誰一人取り残さない」真の意味でのインクルーシブな社会の実現に貢献したいと考えています。それは単なる理想論ではなく、一人ひとりの生徒の成長と幸福を通じて、具体的に実現していくものです。
困難を抱えながらも懸命に生きようとする子どもたちの姿を見るとき、その純粋さと力強さに心を打たれます。彼らの中に秘められた無限の可能性を信じ、その可能性を最大限に引き出すための環境を整えることが、私たち大人の責任であり使命です。
啓明館高等学院は、そのような子どもたちが安心して学び、成長し、やがて社会に貢献する人材として羽ばたいていける場となることをお約束いたします。そして、彼らが将来、次の世代に向けて同じような愛情と支援を注げる大人になることで、真の意味での「循環する社会の仕組み」が実現されるものと確信しています。
皆様お一人おひとりのお力をお借りして、この革新的な教育実践を成功させ、日本の教育の新しい可能性を切り開いてまいりたく、心よりお願い申し上げます。私たちの挑戦は始まったばかりですが、その先に待つ明るい未来を信じて、全力で取り組んでまいります。
どうか温かなご支援とご協力を賜りますよう、深くお辞儀申し上げます。